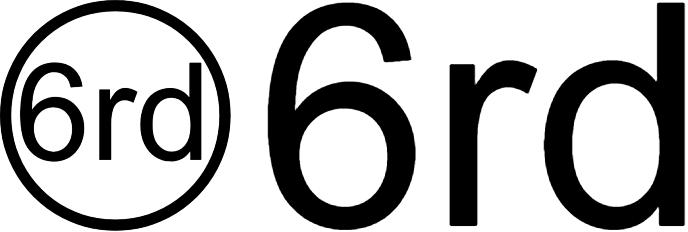私たちの人生は、時に予想もしない道へと導かれることがあります。それは突然の別れだったり、長い間抱えてきた後悔だったり。この物語は、そんな人生の迷路の中で迷子になりながらも、再び自分の居場所を見つけ出す旅の記録です。人は誰しも、心の中に「6rdマイル」と呼べる特別な距離を持っています。それは、最も遠く感じる時に初めて見えてくる、本当の自分との距離なのかもしれません。
突然の別れ
東京の郊外にある小さなアパートで、私は目覚ましの音に目を覚ましました。いつものように7時。いつものように朝の準備をし、いつものようにコーヒーを入れる。そんな平凡な朝が、この日を境に完全に変わってしまうなんて、その時はまったく想像していませんでした。
スマホの画面に表示された母からの着信履歴。5回。普段なら月に一度か二度しか連絡のない母からの不自然な数の着信に、私は胸の奥がキリキリと痛むのを感じました。
「もしもし、お母さん?どうしたの、こんな朝早くから」
受話器の向こうから聞こえてきたのは、かすれた母の声でした。
「お父さんが…昨夜、急に倒れて…」
その後の言葉は、まるで遠くから聞こえてくるようにぼんやりとしていました。父が脳梗塞で倒れ、意識不明の重体だということ。実家のある福岡まですぐに帰ってきてほしいということ。
私の頭の中は真っ白になりました。五年前、父との激しい口論の末に家を飛び出して以来、一度も実家に帰っていなかったのです。父とは一切連絡を取らず、母とも必要最低限の会話しかしていませんでした。
「最後の言葉が口論になるなんて」
その思いが、胸に突き刺さるようでした。
帰郷の道のり
その日のうちに有給を取り、夕方の飛行機で福岡へ向かいました。東京から福岡までの空の旅。わずか2時間の道のりが、この5年間の空白を埋めるにはあまりにも短すぎるように感じられました。
飛行機の窓から見える雲の海を眺めながら、私は父との最後の会話を思い出していました。大学卒業後の進路について。私は東京で新しい可能性を求めたかった。しかし父は、家業の小さな町工場を継いでほしいと願っていたのです。
「お前のためを思って言ってるんだ」
今思えば、その言葉には父なりの愛情が込められていたのでしょう。でも当時の私には、自分の人生を決められることへの反発しか感じられませんでした。
誰でも一度は経験する親子の衝突。でも、その後の5年間の沈黙は必要だったのでしょうか。
福岡空港に着いたとき、思いがけず母だけでなく、幼い頃からの親友である健太が迎えに来てくれていました。彼は変わらない笑顔で私を出迎え、車に乗り込むと自然に会話が弾みました。実家の近所で工務店を継いだ健太は、この5年間の町の変化や共通の知人の近況を教えてくれました。
「みんな、お前が帰ってくるの待ってたよ」
その言葉に、私は複雑な気持ちになりました。自分がいない間も、実家の町は変わらず時を刻み、人々は自分のことを覚えていてくれたのです。
病室での再会
県立病院の集中治療室。消毒液の匂いが漂う廊下を歩きながら、私の足取りは重くなっていきました。
ICUのベッドで横たわる父の姿は、記憶の中の頑固で強い父とはかけ離れていました。チューブや機械に囲まれ、顔色は青白く、体は以前より明らかに痩せていました。
「お父さん…」
声をかけても反応はありません。医師の説明によると、意識の回復は見込めるものの、右半身の麻痺は残る可能性が高いとのことでした。
五年間の空白を埋めるはずの会話ができない現実に、言葉にならない後悔が押し寄せてきました。
病室のソファで一晩中父の側にいた母は、明らかに疲れた表情でしたが、私の顔を見るなり安堵の表情を浮かべました。
「よく来てくれたね」
シンプルな言葉でしたが、その中には様々な感情が込められていました。責めるでもなく、問い詰めるでもなく、ただ子供の帰りを待っていた母の姿がそこにありました。
過去との対峙
父の容体は安定していましたが、意識の回復には時間がかかるとのことでした。私は実家に戻り、数日滞在することにしました。
幼い頃から慣れ親しんだ我が家は、表面上は変わっていないように見えました。しかし、よく見ると至るところに時間の経過を感じさせる変化がありました。リビングの家具の配置、増えた母の趣味の園芸の本、そして何より父の工房が使われていない様子。
母の話によると、私が出ていった後、父は黙々と仕事を続けていたそうです。しかし、一人では町工場の経営が難しくなり、昨年からは大きな工場の下請けとして細々と営業していたとのこと。
「でも、お父さんはね、あなたのことをよく話してたよ」
母の言葉に、私は驚きました。
「東京で頑張ってる子供のことを、周りの人に自慢してたんだよ。『うちの子は大きな会社で設計の仕事をしている』って」
涙が溢れました。父は私のことを認めていてくれたのです。ただ、その気持ちを直接伝えることができなかっただけなのかもしれません。
私たちは時に、最も大切な人に最も素直になれないことがあります。それが、取り返しのつかない後悔につながることを、この時初めて実感しました。
心の6rdマイル
父の工房に足を踏み入れたのは、帰省して3日目のことでした。埃をかぶった工具や材料が、以前と同じように並んでいます。その中で目に留まったのは、作りかけの木製の小さな箱でした。
表面には繊細な彫刻が施されており、蓋には「6rd」という不思議な文字が刻まれていました。
「あれは、あなたの誕生日プレゼントに作ろうとしていたものよ」
後ろから聞こえた母の声に振り返ると、母は寂しそうな笑顔を浮かべていました。
「お父さんが言ってたの。『6rdマイル』というのは、マラソンランナーが一番苦しくなる距離だけど、それを超えると二度目の風が吹いて走りやすくなるって。人生も同じで、最も遠く感じる距離を乗り越えれば、また前に進めるようになるって」
父は私が帰ってくることを信じて、この箱を作っていたのです。しかも、私の誕生日のために。父の手仕事が得意だったことを思い出しました。子供の頃、父が作ってくれた木製の玩具や、修理してくれた自転車。父の大きな手の中で、物が生まれ変わっていく様子を、幼い私はいつも魔法のように感じていました。
そのまま工房に残り、私は父が作りかけていた箱を手に取りました。表面を撫でると、木の温もりと父の思いが伝わってくるようでした。
「6rdマイルを超えるんだ」
私はその瞬間、決心しました。
修復の始まり
翌日から、私は父の工房で過ごす時間が増えました。最初は埃を払い、工具を整理するだけでしたが、やがて父が使っていた工具を手に取り、木材に触れるようになっていきました。
東京の会社には、しばらく休暇を延長することを連絡しました。今はここにいるべきだと感じたのです。
ある日、病院で父の手を握りながら、私は話しかけました。
「お父さん、工房の整理をしてるよ。あの箱も完成させようと思ってる。でも、やっぱりお父さんの腕には敵わないな」
意識のない父に話しかけることは、最初は気恥ずかしく感じましたが、次第に自然と言葉が溢れてくるようになりました。東京での仕事のこと、一人暮らしの苦労、そして心の奥底にあった父への思いも。
「実は、東京に行ってからずっと、お父さんの仕事を否定していたことを後悔してたんだ。実はね、私の設計の仕事も、お父さんから教わった『ものづくりの精神』があったからこそ続けられたんだって、最近やっと気づいたよ」
言葉は空気中に消えていきますが、その振動は確かに心に届きます。たとえ聞こえていなくても、伝えることの大切さを私は学びました。
奇跡の兆し
帰省して2週間が経った頃、父の指先がわずかに動いたのです。医師によると、意識の回復の兆候かもしれないとのこと。
それからは毎日、私は父と話す時間を増やしました。自分が手がけている父の箱のこと、町の変化のこと、そして何より、父と分かち合えなかった5年間のことを。
「お父さん、聞こえてる?私ね、東京でね…」
そんな日々が続いて3週間目のこと。私が父の手を握りながら話していると、かすかに父の指が私の手を握り返したのです。
「お父さん!」
父の目がゆっくりと開きました。
その後の回復は医師も驚くほど早く、一週間後には会話ができるようになりました。右半身の麻痺は残るものの、リハビリによって少しずつ良くなっていくとのことでした。
「…ごめんな」
病室で二人きりになったとき、父は絞り出すように言いました。
「いや、こっちこそ…ごめん」
私たちは言葉少なに、でもお互いの気持ちを理解し合いました。時には、長い沈黙も必要なのかもしれません。その沈黙の先に、新たな理解が生まれることもあるのです。
新たな一歩
退院の日、父は私が完成させた箱を見て、静かに涙を流しました。私の拙い技術で仕上げた箱は、父の作品に比べれば粗削りなものでしたが、父はそれを宝物のように大切に抱えていました。
「よくやった」
シンプルな言葉でしたが、私にとってはこの上ない褒め言葉でした。
東京に戻る前日、私は父と二人で工房に座っていました。父の右手はまだ自由に動かせませんでしたが、左手で私に木工の基本を教えてくれました。
「この町工場、どうするつもりだ?」
父の質問に、私は正直に答えました。
「東京の仕事は続けたいけど…月に一度は帰ってきて、一緒に工房を守っていきたい。それに、将来的には両方できる方法を考えたい」
父は満足そうに頷きました。
「そうか。それがお前の道なら、応援する」
人生の道筋は一つではありません。時に遠回りすることで見える景色もあります。そして、その遠回りこそが、自分自身を見つめ直す大切な時間なのかもしれません。
心の距離
東京に戻った今も、私は月に一度は実家に帰るようにしています。父のリハビリは順調で、少しずつですが右手も動かせるようになってきました。
最近では、父と一緒に小さなプロジェクトを進めています。私が東京で学んだデザインと、父の伝統的な技術を組み合わせた新しい家具のシリーズです。
「こんなこともできるんだな」
新しい可能性に目を輝かせる父の姿を見ると、心が温かくなります。
振り返れば、あの「6rdマイル」は私にとって必要な旅だったのかもしれません。最も遠く感じる距離を経て、初めて見えてくるものがあるのです。
人生には、失うものもあれば、再び手に入れるものもあります。大切なのは、その過程で自分自身と向き合う勇気を持つことではないでしょうか。
そして今、私は自信を持って言えます。たとえどんなに遠く離れていても、心と心の距離は、一歩踏み出す勇気さえあれば、いつでも縮めることができると。
人生の転機に立ったとき、あなたならどうしますか?
この物語を読んで、もし少しでも心に響くものがあったなら、それはきっと、あなたの中にも似たような経験や感情があるからかもしれません。
家族との関係、仕事と人生のバランス、過去の後悔や未来への不安。私たちは誰しも、自分だけの「6rdマイル」を持っています。
その距離を乗り越えたとき、新しい風が吹き始めるのです。
今日も誰かが、自分の「6rdマイル」に向かって一歩を踏み出そうとしています。あなたもその一人かもしれませんね。